
ピラティスのダイエット効果

ピラティスのダイエット効果について、パーソナルトレーナーおぜきとしあきが、解説します。
ピラテスで「痩せた気がする」は、本当に脂肪が減ったのか
ピラティスをしたあとに「身体が軽くなった」「ウエストが締まった気がする」と感じた経験は、多くの人にあると思います。姿勢が整い、呼吸が深くなり、体の内側にエネルギーが通ったような感覚——それは確かに心地よい変化です。
しかし、その変化を「ダイエット効果」と混同すると、本質を見誤ります。ピラティス後のスッキリ感や引き締まりは、体脂肪が燃焼した結果ではなく、神経・循環・姿勢の再調整による感覚的変化です。代謝学的に見ると、1回のピラティスで減る脂肪量はほぼゼロに等しい。
では、なぜピラティスでは体脂肪が減りにくいのか? それを「感覚」ではなく、生理学・代謝学・力学という客観的な視点から解き明かしていきます。
ピラティスは「脂肪が燃える運動」ではない
ピラティスは、体幹の安定と動作のコントロールを目的に生まれた運動体系です。姿勢の改善や関節の可動域の向上、呼吸の最適化などに大きな効果を持っています。
その根底にあるのは「神経的な使い方の再学習」、すなわち脳が筋肉を正しく動かす感覚を覚え直すことです。体幹の深層筋を呼吸とともに働かせることで、体の中心から四肢へとエネルギーが連動する。この「正しい筋の使い方」を取り戻すことこそが、ピラティスの真価です。
しかし、代謝学的に見ると、この運動は「燃やす」ための設計ではないのです。ピラティスでは、動作の振幅(移動距離)が小さく、動作速度も緩やか。心拍数も有酸素運動や筋力トレーニングほど上がらないため、エネルギー消費量は限定的です。
ピラティスは体を“正しく使えるように整える運動”であって、“脂肪を燃やす運動”ではありません。それは悪いことではなく、むしろ「整える」ことが「燃やす」準備になるというのが正しい理解です。
身体のカロリー消費
1日の総消費エネルギーは、次の3要素で構成されています。
- 基礎代謝量(約70%)
何もしていなくても生命維持のために使われるエネルギー。筋肉量が多いほど高い。 - 活動代謝量(約20〜25%)
歩く・立つ・運動するなど、体を動かすことで消費されるエネルギー。 - 食事誘発性熱産生(約10%)
食事を消化・吸収するときに発生する熱エネルギー。
つまり、ダイエットで効果を出すには、①筋肉を増やして基礎代謝を上げる、または②運動して活動代謝を増やす、のどちらかしかありません。
ピラテスと活動代謝
活動代謝とは、言い換えれば「体をどれだけ動かしたか」に比例します。物理学的には、仕事(=力×距離)で表せます。力は「質量×重力加速度」、つまり体重と移動距離の掛け算です。活動代謝は「質量×移動距離×重力」で決まります。
たとえば、ウォーキングやランニングのように体全体を前方へ運ぶ運動は、1時間で200〜400kcalを消費します。一方、ピラティスのように「その場で関節を制御する運動」は、体全体の移動距離が極端に小さいため、同じ1時間でも150〜200kcal程度しか消費しません。
ピラティスの多くの種目は、仰向け・四つ這い・座位といった非荷重位で行われます。重力の影響が分散される体位では、抗重力方向に働く筋肉の活動が減り、心拍数も上がりにくい。つまり、物理的な「距離の移動」が少ないため、距離の移動による活動代謝量はほぼゼロに近いです。
「きつい」「効いている」と感じても、それは筋肉の協調や張力の感覚に対する神経的反応であり、物理的な仕事量(=カロリー消費)とは別の現象です。
ピラテスと基礎代謝
次に基礎代謝量です。これは安静時に消費されるエネルギーですが、そのおよそ70%以上が筋肉量に比例します。筋肉は身体の中で最もエネルギーを使う組織であり、筋肉が1kg増えると、1日あたり約50kcal前後の基礎代謝が上昇すると言われています。基礎代謝を上げるには“筋肉量”を増やす必要があります・
しかし、ピラティスの動作は抗重力下で強い筋収縮を伴わないため、筋断面積が増えるような筋肥大(筋量の増加)はほとんど起こりません。
筋生理学的に言えば、筋肉量を増やすためには、筋が収縮と伸展を繰り返しながら、筋線維自体に適切な重さ(張力)がかかることが絶対条件です。この状態で初めて、筋線維内のタンパク合成シグナルが活性化し、筋膜・サテライト細胞・ミオフィブリルの再構築が進み、結果として筋肥大が起こります。
しかし、ピラティスのように仰臥位や四つ這いといった体位で行う運動は、重力方向に抗する負荷が小さく、筋自体が張力を受ける時間(タイム・アンダー・テンション)も短いのです。そのため、筋肉は「使われている」にもかかわらず、体型的に「育つ」ための条件を満たしていません。
ピラティスは神経的な制御や筋の協調には優れていますが、筋肥大を引き起こす張力学的・代謝的刺激(機械的張力・代謝ストレス・微細損傷)がほとんど発生しません。つまり、筋肉は“使っているけれど増えてはいない”という状態です。
結果として、ピラティスは、筋肉量は増えず、基礎代謝量も上がらない。これが、ピラティス単体でのダイエット効果がかなり限定的な理由のひとつです。
マシンピラティスは筋肉量が増えない
最近では、「マシンピラティス」という言葉をよく耳にします。リフォーマーやキャデラックなどの専用マシンを使うことで、あたかも“筋トレのような負荷運動”に見えるため、「マットよりハード=痩せる」と誤解されがちです。
しかし、リフォーマーのスプリング(ばね)は筋肉に重さを与えるためではなく、動作を補助し、正しい軌道へ導くためのものです。つまり、スプリングの抵抗は「負荷」ではなく「誘導」です。
マシンピラティスの目的は「筋力を鍛えること」ではなく、「動きの精度を上げること」。筋生理学的に見ても、スプリングの抵抗は短時間で解放される弾性負荷であり、筋肥大を起こすほどの等尺性・等張性収縮による張力は維持されません。
むしろ、動きがガイドされるぶん、関与する筋線維数は減る傾向にあります。したがって、マシンを使うことで筋トレ化するわけではなく、代謝的にもマットと大差はありません。「マシンピラティスは痩せる」という宣伝は、科学的には根拠が薄いのです。
マシンピラティスは、筋肉量が増える筋トレではありません。筋肉を動かすことと筋肉量が増えることとは別ものです。
ピラテス後に「引き締まった」の理由
ピラテス後に「引き締まったように見える」のには、理由があります。
ピラティス直後に感じる見た目の変化は、主として次の生理的現象によって説明できます。
- 筋スパズムの軽減:過緊張が抑えられ、筋腹の不要な張りが落ちる。
- 体液循環の改善:血流やリンパの流れが促進され、むくみが軽減する。
- 姿勢の再配置:胸郭や骨盤の位置関係が整い、シルエットがすっきり見える。
- 固有感覚の向上:身体の操作感覚が高まり、動きが軽く見える。
これらは価値ある即時効果ですが、脂肪細胞の減少や筋線維束の増大といった質量の変化ではありません。体感の良さを体脂肪減少と混同しないことが重要です。
ピラテスでは抗重力筋が働かない
抗重力筋が働かないと、筋肉量は増えず、代謝は上が離ません。
日常の立位を支える抗重力筋は、重力を正面から受ける姿勢でこそ強く働きます。代表的な筋群は次のとおりです。
- 頸部伸筋群(頭部の支持)
- 脊柱起立筋群・多裂筋群(体幹の垂直保持)
- 大殿筋・中殿筋・ハムストリングス(骨盤と股関節の安定)
- 大腿四頭筋・下腿三頭筋(下肢の支持)
仰臥位・座位・四つ這いといった非荷重位が中心のピラティスでは、これらの筋群が立位の条件と同レベルで発火・収縮する機会が限られます。そのため、立位での支える力としての再教育が進みにくく、安静時代謝の底上げにも直結しにくいのです。
ピラテスの動きに慣れると省エネ化が進むパラドックス
ピラティスの動きに慣れると、同じ動作をより少ないエネルギーでこなせるようになるため、消費カロリーは下がる場合があります。ピラテスの動きに慣れれば慣れるほど、ダイエットの成果は生じにくいというパラドックスが起こり得ます。
ピラティスの強度を上げれば痩せるのか
ピラティスの強度を上げれば痩せるのかというと、答えは「限定的」です。立位で行う動きや荷重位の姿勢、連続的な反復、そして時間をしっかり確保すれば活動代謝は多少増加します。しかし、体全体の移動距離という観点から見ると、有酸素運動(歩行・ランニング・自転車など)ほどのカロリー消費には届きません。ピラティスは筋肉を「感じて使う」トレーニングであり、「距離を動かして燃やす」トレーニングではないのです。
ピラティスでダイエット効果を出したい場合
ピラティスは、単体では大きな体脂肪減少を引き起こす運動ではありませんが、「痩せるための準備を整える運動」として取り入れることはできます。
ピラティスをやりながらダイエットしたい場合
ピラティスをすることを否定する必要はまったくありません。ピラティスがエクササイズとして好きならやるのは良いと思います。しかし、前述の通り、ピラティス単体でのダイエット効果はほぼ皆無であることを認識することが重要です。その上で、ピラティスの位置づけを正しく理解し、次のように組み合わせることもできるかもしれません。
- ウォームアップとして活用:呼吸・胸郭・骨盤の調律を先に行い、その後の筋トレの出力を引き上げる。
- クールダウンとして活用:筋肉の過緊張を落として回復を促進し、週当たりの総運動量を維持しやすくする。
- 立位・荷重位のピラティス要素を増やす:片脚立位、ヒップヒンジ、スクワットパターンなど重力下の制御練習を取り入れる。
- 週内の総仕事量を設計:ピラティス(整える)+筋トレ(筋肉を増やす)のセット。
- 食事の整合:ストレス低減による過食抑制など間接効果は期待できるが、エネルギーバランスは別途管理する。
ピラティスの効果のまとめ
| プラス効果 | 欠けている要素 | |
|---|---|---|
| 神経制御 | 動作意識・深部筋の協調・感覚入力の改善(神経系の再起動) | 持続的張力の再構築(立位での固定化) |
| 力学的再構成 | 一時的に筋活動の分布を変える(過緊張抑制・軌道再学習) | 抗重力下での筋出力再教育(重力を受ける条件での支え方) |
| 体型的変化 | 血流・筋弛緩・可動性改善(むくみ軽減・こわばり緩和) | 筋断面積・張力方向の再形成(筋肥大・関節角度の恒常変化) |
| 代謝 | 主観的軽快感や省エネ化で日常動作が楽になる | 消費カロリー増や運動後過剰酸素消費(EPOC)の増大は限定的 |
その他、ピラテスについて
各種ボディメイク一覧

|

|
|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
パーソナルトレーナーおぜきとしあき
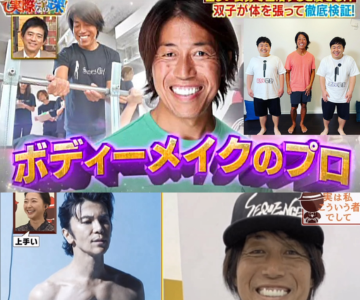
|
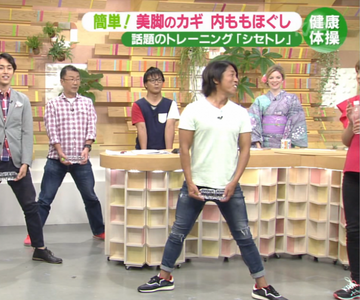
|
|---|

|

|
|---|---|

|

|